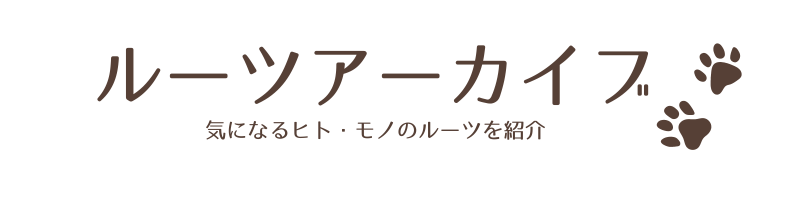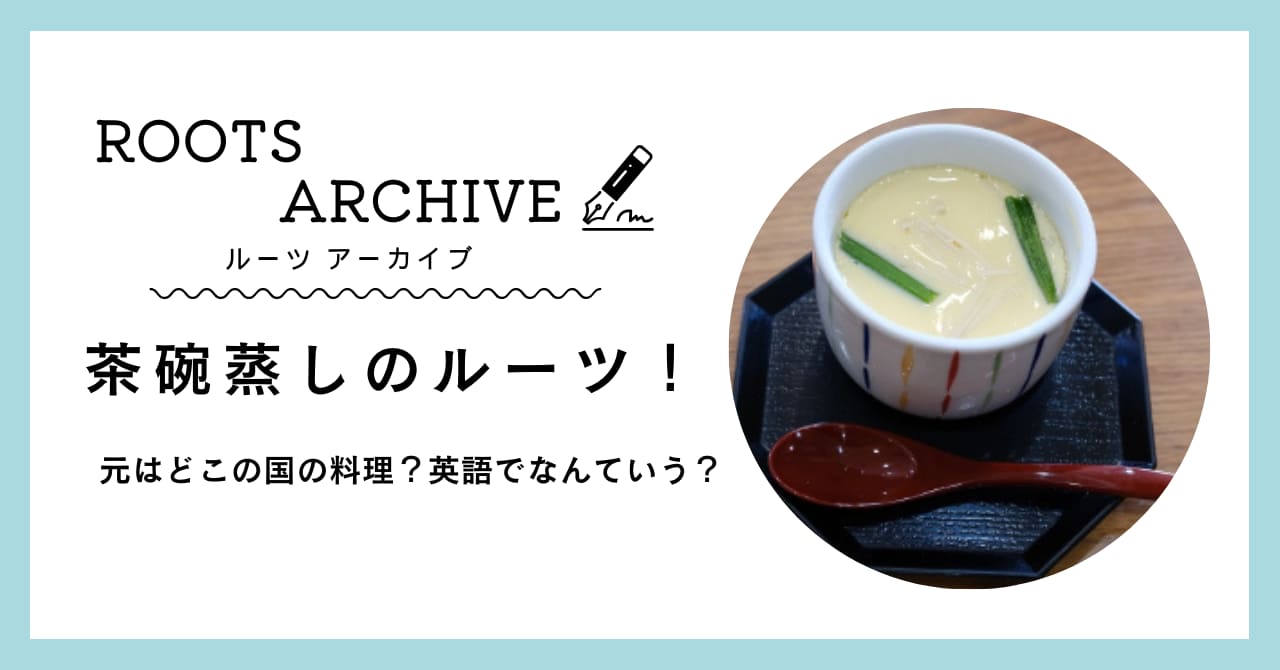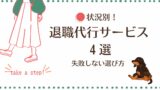卵の風味とお出汁の香り、なめらかな食感の茶碗蒸し。
元はどこの国の料理なの?元祖は?英語でなんていうの?…気になることがたくさん。
当記事を読むと以下のことが分かります!
- 茶碗蒸しのルーツ
- 茶碗蒸しを作った人(元祖)
- 茶碗蒸しの英訳
興味がある方は読んでみてください。
関連記事➟【いなり寿司のルーツ!狐はなぜ油揚げが好きなのか?】
茶碗蒸しのルーツ
「茶碗に食材を入れそのまま蒸す」という調理方法から「茶碗蒸し」と名付けられました。
茶碗蒸しは、1689年江戸時代に長崎で中国人との交流のなかで生まれた卓袱(しっぽく)料理の献立のひとつとして出されていた料理がルーツとなっていると言われています。

卓袱(しっぽく)料理は別名「和華蘭(わからん)料理」とも言われ、日本(和)、中国(華)、オランダ(蘭)の料理がまざりあう宴会料理です。
円卓を大人数でかこみ、大皿から料理を直箸で取り分けて食べるのが作法だそうです。
お刺身や豚の角煮、ポットパイのような「パスティ」というオランダ料理が献立にラインナップされています。

茶碗蒸しは、日本・中国・オランダの料理人のアイデアが融合して生まれたのかな
また、静岡県袋井市のB級グルメ「たまごふわふわ」が茶碗蒸しの原型という説もあります。
引用:袋井市ホームページ 「たまごふわふわ」
「たまごふわふわ」は泡立てた卵を煮立てたお出汁に流し込んで、ふんわりと仕上げた料理。
江戸時代には名物料理として知られていて、日本最古の卵料理とされているそうです。
茶碗蒸しの種類(別名)
茶碗蒸しの種類、小田巻き蒸し(信太蒸し)と玉地蒸しについて紹介します。

どっちも美味しそう!
茶碗蒸しが甘い地域がある
北海道、青森、秋田の一部では甘い茶碗蒸しが存在します。
銀杏の代わりに栗の甘露煮を入れ、出し汁にも砂糖を加えて甘く仕上げるそうです。

北海道や東北地方の一部では赤飯も甘いんだよね
茶碗蒸しを作った人
寛政時代(1789年〜1801年)にはすでに存在し、関西地域を中心に食されていたという茶碗蒸し。
伊予松山の藩士だった吉田宗吉信武(よしだ そうきちのぶたけ)は、初めて長崎で茶碗蒸しを食べ、その美味しさに感動。
宗吉信武は1866年「吉宗(よっそう)」の屋号で茶碗蒸しと蒸し鮨のお店を開業しました。
そんな「吉宗(よっそう)」は令和となった現在も長崎県で「長崎の元祖茶碗蒸し」のお店として営業しています。
引用:たびらい 吉宗(よっそう)の「吉宗定食」
吉宗(よっそう)の店舗は、昭和2年に建てられたものを現在まで使用していて、レトロな雰囲気が素敵です。
伝統の味を守りつづけている丼サイズの茶碗蒸しと蒸し鮨を、長崎観光の際にはぜひ味わいたいですね。
【PR】茶碗蒸し作りのおだしにオススメ
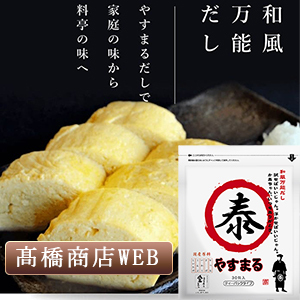
茶碗蒸しは英語でなんていう?
茶碗蒸しは西洋にはない料理なので、そのまま「chawanmushi」と直訳されます。
chawannmushiって何?となった場合は
などと説明するそうです。
記事作成を手伝ってくれたのはラクリン
ラクリンはブログ記事作成に特化したAIツールです。
本文の作成はもちろん、キーワードの提案やSEOを考慮した見出しの作成もしてくれます。

その他、リード文やまとめ文、ディスクリプションの作成機能もありますし、リライトや誤字脱字チェックなどブロガーが欲しい機能を備えています。
事前学習機能で文章の雰囲気を調整できるのもラクリンの強みです。
完全無料のフリープランは、ID(ニックネーム)とメールアドレス、携帯電話番号だけですぐに使い始められます。
| プラン | 月額料金(税込) | 作成可能記事数/月 | 1記事あたり料金 |
|---|---|---|---|
| フリー | 0円 | 約2記事 | − |
| シルバー | 4,980円 | 約50記事 | 約100円 |
| ゴールド | 9,980円 | 約150記事 | 約67円 |
| プラチナ | 29,980円 | 約500記事 | 約60円 |
フリープランだと作成できる記事数や使える機能に制限はありますが、AIをお試しで使ってみたい方にはぴったりです。
ラクリンが使い方をわかりやすく説明してくれるので初心者でも大丈夫。

超初心者のぼくもすぐ使えたよ
ライターさんに外注したら1記事100円以下でなんて受けてもらえません。それにラクリンなら体調不良などライターさんの都合で納期に間に合わないなんてこともありません。
月額0円のフリープランへの登録に必要なのは、ID(ニックネーム)とメールアドレス、携帯電話番号だけ。
有料プランへの変更はいつでも自由にできます。(有料プランはクレジットカードの登録が必要)
Rakurin(ラクリン)公式サイトまたフリープランを使い続けたからといって、有料プランへのしつこい勧誘もありません。
ぜひフリープランに登録して無料でAIを使った記事作成を体験してみてください!
茶碗蒸しのよくある質問
- Q茶碗蒸しのルーツは?
- A
茶碗蒸しのルーツは長崎の卓袱料理の料理のひとつ。元祖は吉田宗吉信武が創業した「吉宗(よっそう)」だと言われています。
- Q茶碗蒸しの正しい食べ方は?
- A
お箸で全体をかき混ぜて吸い物のように飲むのが正しいという見解もありますが、スプーンやレンゲですくって食べても問題ないという記述もあります。
- Q茶碗蒸しの英語名は?
- A
「chawanmushi」です。どんなものか説明するなら「steamed egg custard」や「Japanese steamed egg pudding」。
まとめ
茶碗蒸しのルーツや元祖(作った人)、英訳について調査しました。
230年ほど前から日本で食されていたという茶碗蒸し…奥深いですね。